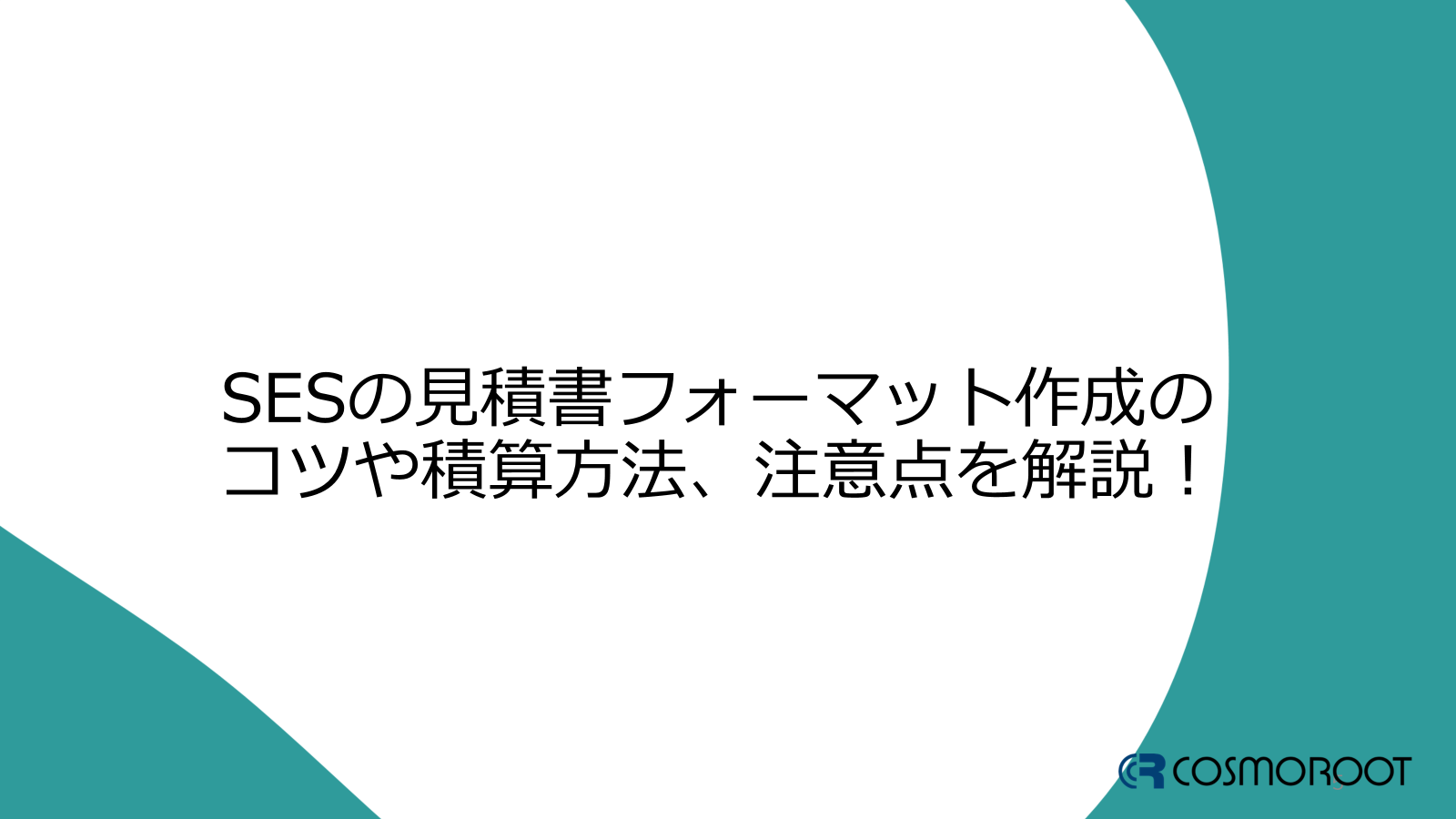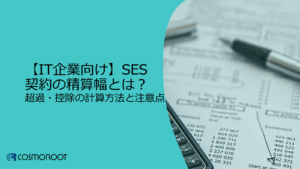SES契約で見積書を作成する際、Web開発のように工程ごとに積算を行うことが少ないです。「人月(にんげつ)」という工数を表す単位で見積もりをするのが一般的です。
SES契約を結ぶ場合、どのように見積書を作成すればよいのでしょうか。
本記事では、初めてSES契約の見積書を作成する方に向けて、記載すべき項目や顧客と認識をそろえておくべき前提条件などを解説します。
見積書作成に不安を感じている方はぜひ最後まで読んでみてください。
SESの見積書とは

見積書は、SES契約の締結前に目安となる金額を顧客に提示するものとして作成される書面です。
SESの見積書では、エンジニアの人件費を人月単価で計算し、交通費などの諸経費を積み上げて見積金額を算出します。Web開発の見積もりのように、要件定義や基本設計、開発費用などの各工程で必要な工数から金額を計上する方法とは異なります。
これは、SES契約が開発をした成果物に対して報酬が支払われるのではなく、エンジニアが作業を行ったという役務に対して支払われるためです。そのため、SES契約においてはエンジニアの経験年数や保有スキル、役職などによって人月単価が上がり、見積金額も高くなります。
SESの見積書に記載すべき項目
一般的なSESの見積書に記載すべき項目は次の通りです。
- 発行日
- 見積番号
- 宛先
- 件名
- 作業条件(作業場所や納品物(作業実績報告書など)、納期)
- 支払い条件(月末締め翌月末支払いなどの支払いサイト)
- 有効期限
- 提出者の会社名など
- 提出者の捺印
- 見積金額
- 名称(SESの場合、役割や職位と作業期間を記載するのが一般的)
- 単価(1人月の単価を記載するのが一般的)
- 数量
- 金額
- 超過・控除精算の方法
- 小計
- 消費税
- 合計金額
- 備考
納品物について
SESでは成果物ではなく、エンジニアの労働力を提供したことに対して報酬が支払われます。そのため、納品物の欄にはエンジニアが役務提供を行ったことを顧客に示す作業実績報告書(勤務表)などを作成します。
作業期間終了後または長期契約においては一定期間ごとに、作業実績報告書を顧客に提出するのが一般的です。
名称・単価について
名称・単価の欄には、SESの場合、役割や職位と作業期間を記載するのが一般的です。2ヶ月以上作業期間がある場合は、数量欄に月数を記載して、人月単価に月数を乗じた数値が見積金額となります。
作業期間について
作業期間については、見積書作成を依頼された際に指定の開始時期があれば、そちらを始期として記載しますが、特段指定がない場合は仮の作業開始日を始期とする作業期間を記載します。
仮の作業開始日は、見積書の有効期限内であればいつ発注しても作業を開始できる日を記載するか、「発注日から〇日後を作業開始日とする」と備考欄に記載するなどの手法を取るのが一般的です。いずれにおいても見積書を見た顧客から急な発注があった際に、対応できなくなる事態を避けられるように記載しましょう。
見積金額の計算方法

見積金額は、エンジニアの人数とそれぞれの人月単価に作業期間を乗じたものに諸経費を加えて算出されます。見積金額の大部分を占めるエンジニアの役務提供費は、「人月(にんげつ)」と呼ばれる単価で計算されます。
人月単価は、経験年数や扱える言語、技術力、役職などで変動するため、プログラマーやテスターよりも、システムアーキテクトやプロジェクトマネージャーの方が高くなるのが一般的です。
人月単価とは?
人月単価とは、1人のエンジニアが1ヶ月稼働した場合に顧客に請求する金額です。人月単価は、あらかじめ決められた1ヶ月あたりの労働時間(例:8時間×20日=160時間)に対する金額になります。
金額に含まれるものとしては、所属元のSES企業がエンジニアに支払う給与やバックオフィスにかかる経費、SES企業のマージンなどを積み上げて計算されています。
見積書作成時の前提条件
想定していなかった事態が契約履行時に発生しない限り、見積書に記載された金額で発注できると顧客に提案するために見積書は作成されます。
そのため、事前に前提条件のすり合わせを行ってから見積書作成に入ると、本契約に入る段階で金額修正や再協議が不要になることや、契約後にトラブルになる確率を下げることが可能です。
本章では、SES契約の見積書作成時に、契約当事者間でそろえておくべき前提条件を解説します。
- エンジニアのスキルセット・作業内容
- 作業期間
- エンジニアの勤務時間・出勤日数
- 勤務場所
それぞれ詳しく見ていきましょう。
エンジニアのスキルセット・作業内容
顧客が求めている言語や技術力、エンジニアに依頼したい作業内容を事前に確認し、必要なスキルを持ったエンジニアの単価を基に見積金額を算出しましょう。両者の認識にズレがあると、業務開始後に顧客からエンジニアの交代要望や、金額の値引きを求めるクレームが入るなどの問題が発生する可能性があります。
反対に、事前に聞いていた内容と作業内容が異なることについて、エンジニアから不満の声が上がってくる場合があります。顧客・エンジニアそれぞれとの信頼関係が崩れる要因にもなるため、依頼内容のすり合わせは必須です。
作業期間
作業期間も見積書を作成する際によく確認しておきましょう。期間が変動すれば、見積金額にも大きな影響を及ぼします。また、契約締結後に顧客から期間の延長について要望があっても、エンジニアが次の客先へ参画することが決まっているなどの事情で対応できず、トラブルにつながる可能性があります。
また、作業期間をすり合わせる際には、顧客が何を目的としているのかヒアリングも必要です。たとえば、顧客がシステムの完成を目的に作業期間を設定している場合、SESは成果物の納品が報酬支払の要件ではないことを伝えた上で、契約に進まないとトラブルになる可能性があります。
エンジニアの勤務時間・出勤日数
人月単価に大きく影響するエンジニアの1日あたりの勤務時間と出勤日数についても、事前に調整しておく必要があります。SESは準委任契約の一形態として扱われることが多いため、顧客からエンジニアに対して残業を命令できないことも伝えておきましょう。
また、勤務時間が見積書作成時の想定より超過する場合には、超過時間によって超過精算を行うことも見積書の備考欄などに盛り込んでおくとよいです。
勤務場所
エンジニアが常駐する勤務場所について、場所の確認や在宅勤務などのフルリモートが可能なのか、よく確認をしておきましょう。顧客の事務所へ出勤が必要であれば、交通費などを経費として見積書に盛り込みます。
顧客の事務所へ出勤が必要な場合、場所によっては対応できないエンジニアもいます。勤務場所も加味した見積書の作成が必要です。
見積書作成時の注意点

次に見積書作成時に気をつけるべきポイントを紹介します。どのようなポイントに注意して見積書を作成すればよいかわからない方は参考にしてみてください。
- 前提条件が抜けていないか
- 金額の根拠は明確か
- 費用の抜け漏れはないか
- 必要に応じてバッファを積んでいるか
- 超過・控除精算の方法を明記しているか
それぞれ詳しく解説します。
前提条件が抜けていないか
前章で紹介した、見積書作成時に必要な前提条件について記載漏れや、顧客への確認漏れがないか提出前にチェックしましょう。「この場合はどうなるか?」と具体的な状況を想定しながら確認すると、抜けや漏れに気づきやすいです。
少しでも気になる点があれば、営業担当とやり取りのうえ、必要に応じて顧客へ確認を行うと、想定外の事態が発生してもトラブルを防ぎやすくなります。
金額の根拠は明確か
見積もりの積算根拠を顧客に説明できるようにしておくことで、見積金額を提示した際に「高すぎる」と言われたり、値引き交渉を受けたりした際に、建設的な話し合いが行えます。
たとえば、エンジニアの技術レベルや役職に応じた人月単価の目安資料や、サンプル事例における見積金額などを資料として用意しておくと、説明がしやすくなるでしょう。併せて社内資料として、原価とマージンの内訳がわかるような資料も作成しておくと、値引き交渉を受けた際にも、値引きできる金額を営業担当者が見極めやすくなります。値引き交渉にその場で応じられると、契約に向けた話し合いがスムーズに進められます。
費用の抜け漏れはないか
見積書の提出にあたって、顧客に請求すべき費用の記載漏れがないか確認しましょう。契約後に記載漏れに気づいても、顧客に追加請求を行うとトラブルにつながる可能性が高いため、請求できずに赤字になってしまいます。
必要に応じてバッファを積んでいるか
想定外の事態が発生した場合に備えて、見積金額にバッファを積んでおくことも大切です。バッファを積んでいないと、見積書作成時には想定していなかったことが発生した際に、追加費用を顧客に都度請求しなければ赤字になってしまいます。
顧客にとっても何かある度に、費用が上乗せされていくのは良い気分がしないですよね。
ただし、バッファを過剰に積んでしまうと、見積金額が高くなり契約締結に至らなくなったり、見積もり金額について不満を持たれたりする可能性があります。必要に応じて適正なバッファを積むようにしましょう。
超過・控除精算の方法を明記しているか
基準とする作業時間と実際の稼働時間に差異があった場合に、見積書に超過・控除精算の方法を記載しておくことで、どれくらいの金額を追加請求または減額するのか顧客とトラブルになる可能性を防げます。
具体的には人月単価を算定する際に、月の稼働時間に上限・下限時間を設定し、精算幅を設けます。たとえば、次のようなイメージです。
基本単価:400,000円/月
上限時間:180時間
下限時間:140時間
この場合において、上限時間を上回ってエンジニアが稼働した場合には超過時間に対する追加費用を請求し、下限時間を下回った場合にはその分の報酬を控除して顧客に請求します。
超過・控除精算の方法は大きく次の3つです。
上下割
超過精算を行う場合には基本単価を上限時間で割って得られた金額、控除精算を行う場合には基本単価を下限時間で割って得られた金額で精算を行う方法です。上下割は、超過・控除精算において一般的に用いられる手法です。
金額は先程の基本単価と上限・下限時間を用いた場合、次のようになります。
【超過金額】
400,000円÷180時間=2,222円/時間
【控除金額】
400,000円÷140時間=2,857円/時間
中間割
上限時間と下限時間の中間となる時間で基本単価を割って得られた金額を、超過・控除精算に用いる方法です。中間割の計算は次のとおりです。
(180+140)÷2=160時間(中間値)
400,000円÷160時間=2,500円/時間
固定精算
固定精算では、精算幅を設けずに基本単価のみを支払う方法です。稼働時間を加味しないため、エンジニアにとって過酷な案件となる可能性もあります。
精算幅よりも稼働時間が長いまたは短い場合に、見積もり時に取り決めた方法で超過・控除精算を行います。たとえば、上下割を用いた超過・控除精算は次のとおりです。
基本単価:400,000円/月
上限時間:180時間
下限時間:140時間
(稼働時間190時間の場合)
【超過金額】
400,000円÷180時間=2,222円/時間より、
400,000円+(超過精算:2,222円×10時間)=422,222円(請求金額)
(稼働時間130時間の場合)
【控除金額】
400,000円÷140時間=2,857円/時間より、
400,000円-(控除精算:2,857円×10時間)=371,430円(請求金額)
精算幅と超過・控除精算の方法について、見積書作成時に顧客とすり合わせを行い、明記するようにしましょう。
SESの見積書作成をNeWARPで効率化しましょう
今回はSES契約における見積書作成のポイントや、注意点などを解説しました。見積書は顧客に対する提案や本契約に向けたすり合わせなど、さまざまな意味合いを持っています。
そのため、見積書作成においては必要なポイントをきちんと押さえて顧客へ提出する必要があります。
しかし、継続的に顧客から依頼を受ける場合など、何度も同じ見積書を作成するのは手間がかかりますよね。
NeWARPは、簡単な操作でSESの見積書を作成することができ、過去のデータを用いて作成することも可能なため、同様の見積書を何度も一から作成する必要がありません。
見積書作成からプロジェクト管理まで一括で行えるNeWARPについてもっと詳しく知りたい方は、以下のページからご覧ください。