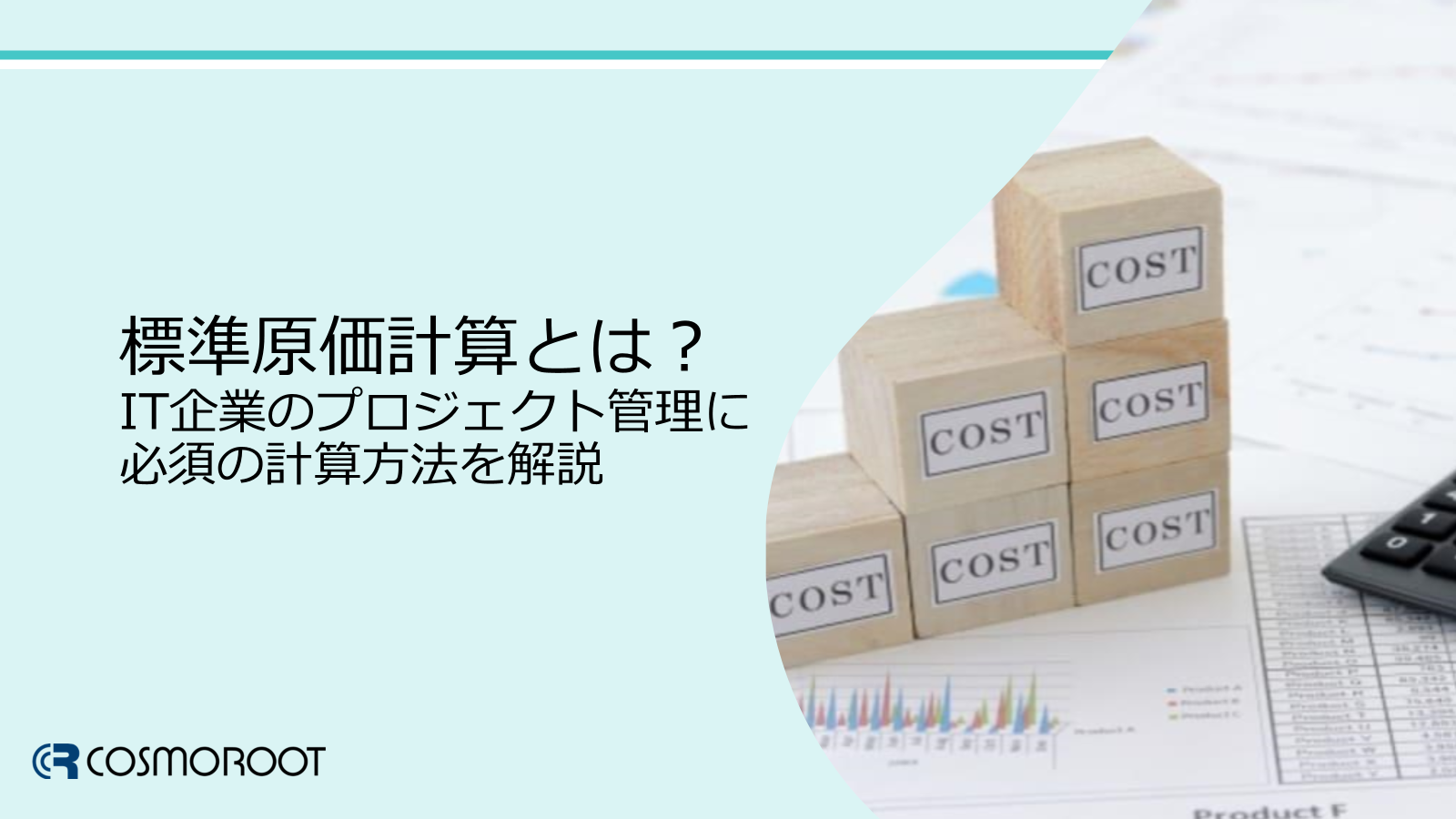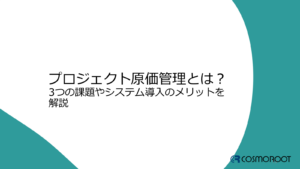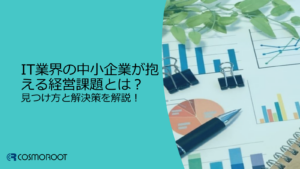標準原価計算とは、製品の開発前に標準的な原価を算定することで、実際に発生した原価と比較し、必要以上にかかったコスト削減策を分析するための手法です。
システム開発においては外注費や人件費などが中心でコストが目に見えにくいため、正確にコスト分析をしたいと考えている企業も多いでしょう。
本記事では、原価計算の基礎から標準原価の計算方法と原価差異の分析手法までを詳しく解説します。
最後まで読めば、自社の利益率をアップさせるための考え方が理解できます。
原価計算とは

原価計算とは、製品を製造するためにかかった原価の計算を行うことです。原価とは、材料費・労務費・経費の3つで構成されます。
IT業界においては、開発にあたって使用した消耗品などが材料費、開発にあたったエンジニアの人件費などが労務費に該当します。経費は外部協力会社へ支払った外注委託費やサーバーの保守費用、打ち合わせに要した交通費などです。
ただし、ソフトウェア開発においては、材料費はほとんどかからず外注委託費が大きな割合を占めます。そのため、IT業界における原価計算は、労務費・外注委託費・経費の3つを主な要素として計算するのが一般的です。
直接費と間接費
原価計算においては、原価を直接費と間接費に分けて考えます。直接費は製品開発に直接的にかかる費用です。たとえば、そのプロジェクトだけに携わるスタッフの人件費や外注委託費、打ち合わせのための交通費・飲食費などが挙げられます。
間接費とは、間接的に製品開発にかかった費用です。たとえば、事務所の家賃や光熱水費、販売管理費などが挙げられます。また、経理や人事など直接的に開発に携わらないスタッフの人件費も間接費に含まれます。
原価計算の種類
原価計算はかかった原価を全て計算する全部原価計算と、変動費のみを原価として扱う部分原価計算の2種類に分類されます。さらに全部原価計算は実際原価計算と標準原価計算に分けられます。標準原価計算は、全部原価計算の中の一つの計算手法です。
また、実際原価計算は総合原価計算と個別原価計算の2種類に分けられます。総合原価計算は、製品を大量かつ長期間にわたって製作する製造業などで用いられる計算手法です。反対に個別原価計算は、受注生産方式やプロジェクト単位で製品開発を行うソフトウェア開発や広告業、建設業などで用いられます。
標準原価とは

標準原価とは、製造に必要な費用を化学的・統計的に算定し、製品の製造前に設定する原価です。実際に製造を行う際の目標値として用いられ、製造後に実際にかかった費用である実際原価と比較します。
標準原価より多くのコストがかかっている部分を特定し、製造工程などに課題があればコスト削減施策を行うことで、コストを抑え利益率の向上が望めます。
標準原価の種類
標準原価は使用目的に応じて算定方法が異なり、次の5つに分類されます。
- 理想標準原価
- 現実的標準原価
- 正常標準原価
- 基準標準原価
- 当座標準原価
コスト分析を行う目的では、主に現実的標準原価や正常標準原価が用いられます。それぞれの標準原価について、順番に見ていきましょう。
理想標準原価
理想標準原価は最も効率よく製品を製造できた場合における標準原価です。スタッフや設備の現実的な稼働率を考慮せず、理想的な最大効率で算定されているため、実際原価との比較よりも他の標準原価を設定する際の参考指標として用いられます。
現実的標準原価
現実的標準原価は、現場の実態に即した現実的な製造効率を基に算定された標準原価です。
スタッフや設備の稼働率を現実的な値に設定したうえで算定されます。また、直近の賃金相場や光熱水費などを反映して設定されるため、比較的短期間で用いられる指標です。
正常標準原価
正常標準原価は、過去の実績値に基づくデータを比較的長期にわたって集計し、平準化したものに将来的な数値の変動を加味して算定された標準原価です。
過去の指標や実際に製造にかかった原価をベースに算定されている点や、将来的な変動を見込んだ長期的な運用を想定している点で現実的標準原価とは異なります。
基準標準原価
基準標準原価は、長期にわたる基準値として設定される標準原価です。設定後は実際原価との差異から設定時との状況変化を分析するために用いられます。
実態に即した標準原価とするために、一定期間ごとに改訂される現実的標準原価や正常標準原価とは用途が異なります。ただし、算定された現実的標準原価や正常標準原価を基準標準原価として設定する場合もあります。
当座標準原価
当座標準原価は、賃金相場や価格要件などの状況変化を反映させるため、毎期改訂される標準原価です。
長期にわたって基準値となる基準標準原価とは対になるものとして扱われます。
標準原価の計算方法

ここからは標準原価の計算方法について解説します。標準原価について理解し、実際にどのようにして用いるのか知りたい方は参考にしてみてください。
標準原価は次の手順で計算されます。
- 標準原価の算定
- 実際原価の集計
- 差異分析
それぞれ順番に解説します。
標準原価の算定
ソフトウェア開発の前に標準原価を算定します。労務費・外注委託費・経費の3つについて、標準的な原価を算定し、その合計が標準原価になります。
標準労務費の計算を式で表すと次の通りです。
標準労務費=予定賃率×標準作業時間
賃率とは、1時間あたりの作業単価です。予定賃率はその年度に予定されている支払賃金と就業時間を基に算出します。標準作業時間は過去の開発実績などを基に妥当な作業時間を割り出します。
外注委託費は、過去の委託実績や事前に取った見積もりなどで標準原価を設定することが可能です。経費は、打ち合わせに必要な交通費やサーバーの保守費用などの事前に想定される費用を積み上げて算定します。
実際原価の集計
開発後、実際に発生した費用を基に実際原価を算出します。ソフトウェア開発における実際原価の計算は個別原価計算によって行います。
実際原価は、実際にかかった労務費と外注委託費、経費の合計値です。
実際労務費は、実際に発生した労務費を各スタッフの作業時間からそれぞれ集計して求めます。外注委託費は、実際に発生した費用を設定します。委託先からの請求書や納品書などで確認するのがよいでしょう。経費は実際に発生した経費について、領収書などを基に集計します。
差異分析
標準原価と実際原価の差異を分析し、実際原価の方が高い場合は要因を特定してコスト削減のための施策を考えます。
PDCAサイクルを、(Plan)標準原価の算定、(Do)実際原価の集計、(Check)差異分析、(Action)コスト削減のための施策実行、と回せば効率的なシステム開発が行えるようになります。
具体的な差異分析の方法は次章で解説するので参考にしてみてください。
差異分析の方法

標準原価と実際原価の差異を具体的にどのように分析するのか、差異分析の方法を具体的に解説します。
ソフトウェア開発における差異分析は主に次の4つの観点から行います。
- 時間差異
- 賃率差異
- 外注委託費にかかる差異
- 経費・製造間接費における差異
それぞれ順番に見ていきましょう。
時間差異
標準労務費よりも実際労務費の方が高い場合、時間差異か賃率差異のどちらかが発生しています。標準作業時間と実際作業時間を比較して、実際作業時間の方が長い場合は、時間差異の分析が必要です。
たとえば、新人エンジニアがプロジェクトにアサインし、業務に慣れるのに時間がかかったためなど、理由を分析しコスト削減策につなげます。新しいスタッフのアサインが理由であれば徐々に慣れ、実際作業時間は縮小されますが、エンジニア間で重複する作業を行っていたなど無駄な作業があれば業務フローの改善が必要です。
特に時間差異は、直接労務費に関わる部分で内部要因に起因するものであるため、しっかり分析しましょう。
賃率差異
予定賃率と実際の賃率を比較して実際の賃率の方が高い場合、賃率差異の分析が必要です。賃率を計算式で表すと次の通りです。
賃率=開発に直接携わるエンジニアの賃金(基本賃金+加給金)÷総就業時間
賃率差異が発生する要因としては、社会規定の変更による給与引き上げや、開発を担当するエンジニアの急な変更などが挙げられます。外的要因に起因するものも多いため、コスト削減策を取るよりも、標準賃率の見直しなどの対策が一般的です。
外注委託費にかかる差異
予定されていた外注委託費よりも実際の発注額が高い場合、外注委託費についても差異分析が必要です。特にソフトウェア開発においては外注委託費が大きな割合を占めているケースも少なくありません。
ソフトウェア開発大手の伊藤忠テクノソリューションズ株式会社の2023年有価証券報告書では、社内発生原価の70%以上を外注費が占めています。
実際に発生した外注委託費が高い場合は、追加作業や業務遂行における障害の発生有無を委託先へ確認しましょう。見積もりが甘かったことによるものなのか、相見積もりや作業条件の明確化など委託の仕方でコストを削減できるものなのか分析し、次回委託時に反映させます。
経費・製造間接費における差異
経費や製造間接費においても、実際に発生した費用の方が高い場合、その要因分析が必要です。
経費については、出張交通費や打ち合わせで使用した飲食代など、必要以上に回数が多かったり、金額の高いものを利用したりしていないか分析します。
製造間接費については、バックオフィス部門の人件費やオフィス賃料の改訂、光熱水費の値上げなど、全社的なコスト増となる要因がなかったかを分析します。
標準原価計算を用いて効率的な製造管理をしましょう

標準原価計算は必要以上にかかっている可能性のあるコスト要因を分析し、利益率の向上につなげるために重要な分析手法です。
しかし、分析にあたっては実際に発生した原価を正確に把握する必要があります。特にシステム開発は各エンジニアがどのプロジェクトのために、どれだけ作業をしたかが見えにくく、精緻な原価計算の難しさを実感している企業も多いのではないでしょうか。
NeWARPは、システム開発のように案件単位で個別に管理を行う必要があるシチュエーションに最適なプラットフォームです。各エンジニアの稼働時間や作業工数をプロジェクト別に管理することや、外注委託費や物品購入なども正確に記録できます。
標準原価計算によるコスト削減に取り組みたい方は、以下のリンクから詳しい情報をご覧ください。