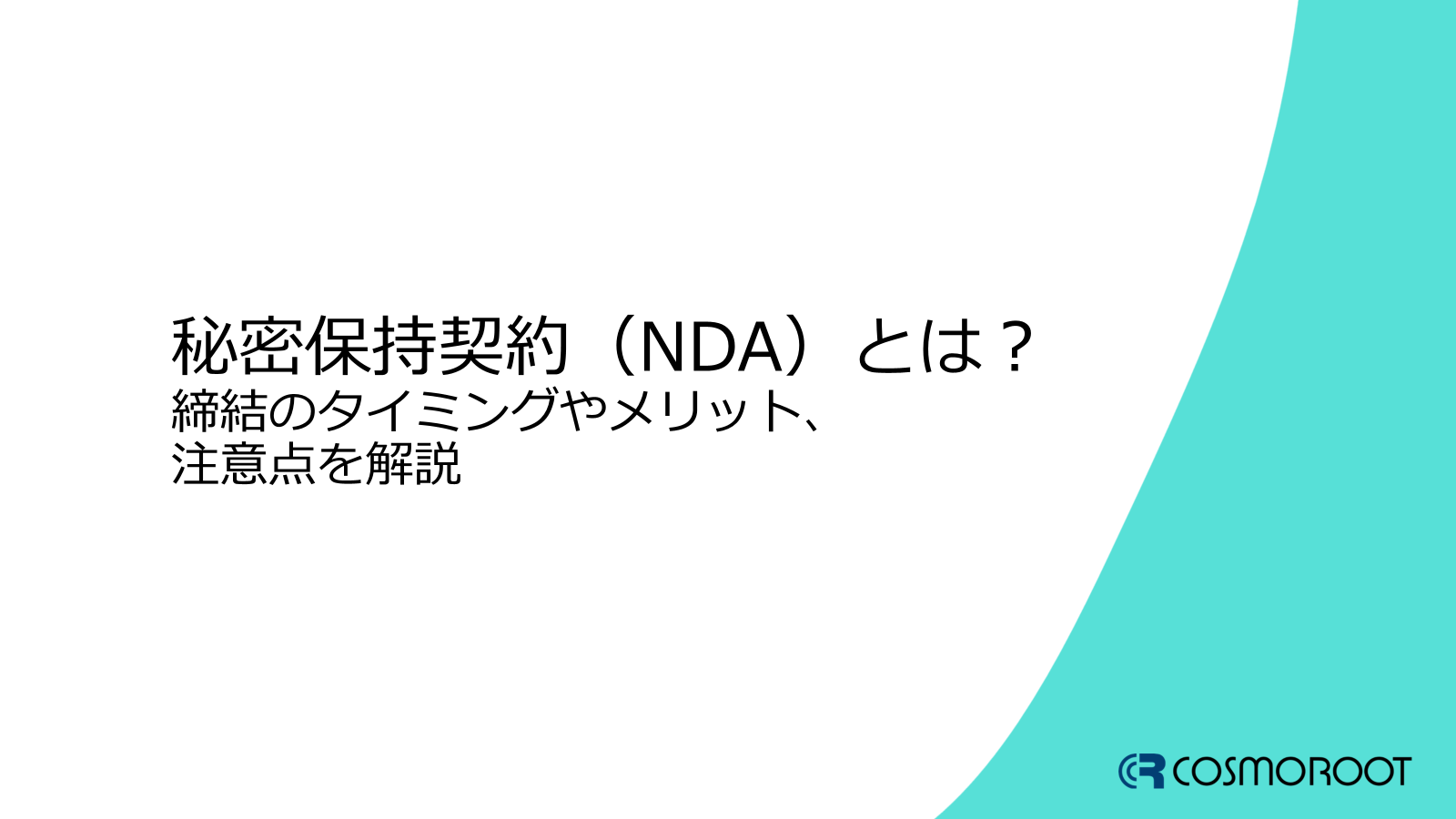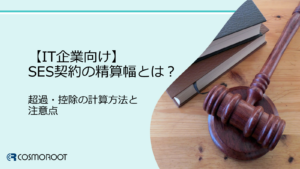秘密保持契約(NDA)は秘密情報の漏えいを防止するために必要な契約です。
しかし、どのタイミングで締結するのが望ましいのか、保護される秘密情報とは具体的にどれなのか理解されている方は多くありません。
本記事では、秘密保持契約によってどのような情報を守れるのか、締結にあたっての注意点などを解説します。
初めて秘密保持契約を締結する方や、秘密保持契約のメリットを詳細に知りたい方はぜひ最後まで読んでみてください。
秘密保持契約(NDA)とは
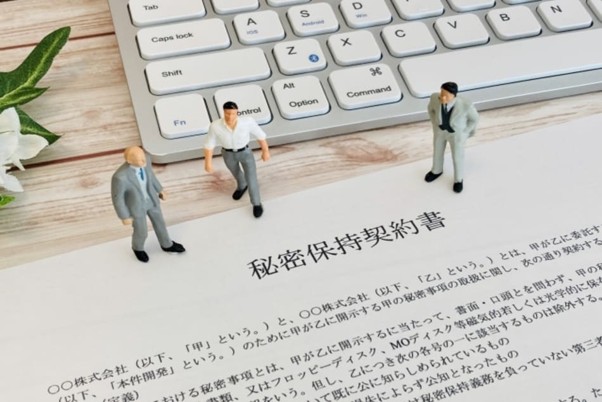
秘密保持契約(NDA:Non-Disclosure Agreement)とは、自社の秘密情報を開示する際、開示した秘密情報を受領者側が取引以外に使用することや、第三者へ開示することを防ぐために締結するものです。機密保持契約やCA(Confidentiality Agreement)とも呼ばれますが、意味合いは同じです。
業務提携や業務委託契約、共同開発など自社が持つ情報を相手方に開示する際に用いられます。秘密保持契約には双方が情報開示を行う双務契約と、一方だけが情報開示を行う片務契約の2種類があります。
秘密情報とは
秘密情報は営業秘密と、それ以外の秘密情報の2種類に分類されます。営業秘密とは、不正競争防止法第2条第6項に規定される情報です。秘密として管理されている情報で、公になっていない生産方法や販売方法、技術上・営業上の有用な情報を指します。経済産業省の「逐条解説 不正競争防止法」では、次の3要素を満たすものとして定義されています。
- 秘密管理性
- 有用性
- 非公知性
それ以外の秘密情報とは、営業秘密には該当しないが、他者に知られたくない情報です。
秘密保持契約(NDA)に法的拘束力はあるか
不正競争防止法第2条第6項に規定する営業秘密を不正に使用・開示などした場合、同法への違反となります。この場合、営業秘密の保有者は秘密保持契約を締結していなくても法的な保護を受けられます。
ただし、営業秘密の3要素(秘密管理性・有用性・非公知性)全てを満たす情報にしか適用されないため、範囲は限定的です。営業秘密以外の秘密情報についても、秘密保持の義務を受領者側に課すために当事者間の契約として秘密保持契約を締結します。
秘密保持契約(NDA)締結のタイミング
秘密保持契約は、秘密情報の開示を行う前に締結するのが望ましいとされ、IT業界では具体的に次のようなシーンで締結します。
- SESで要員募集している案件情報を開示するとき
- 自社のエンジニアのスキルシートを送付するとき
- 下請け業者やフリーランスへの業務委託締結時
- 新規プロジェクトの案を社外のコンサルタントなどに相談するとき
- システム開発の見積もり依頼時、前提条件となる社内データを提供するとき
ただし、実際の契約締結時に合わせて秘密保持契約を結ぶ場合や、契約書の中に秘密保持条項として盛り込む場合もあります。手続き的には問題ありませんが、秘密保持契約締結前に開示された情報は、秘密情報として扱われない可能性があるので、注意が必要です。
秘密保持契約(NDA)のメリット

次に秘密保持契約を締結するメリットを3つ紹介します。
- 秘密情報の漏えいを防げる
- 特許申請を円滑に進められる
- 秘密情報の範囲を設定できる
それぞれ順番に見ていきましょう。
秘密情報の漏えいを防げる
秘密保持契約を締結することによって、不正競争防止法で保護されない営業秘密以外の秘密情報の漏えいも防げます。
万が一情報漏えいが発生した場合には、差止請求や損害賠償請求が可能です。また、秘密保持契約を締結していると、裁判において漏えいした情報が営業秘密であるか判断する際に、判断要素の一つとして扱われる可能性があります。
特許申請を円滑に進められる
秘密保持契約によって営業秘密の漏えいを防ぐことで、特許申請を円滑に進められます。
特許法第29条第1項第1号の規定により、「公然と知られた発明」は特許を取得できません。
営業秘密を用いて特許申請を予定している場合、秘密保持契約によって営業秘密を受領する相手方に対して秘密保持を義務付けることで、特許取得できなくなるリスクを抑えられます。
秘密情報の範囲を設定できる
秘密保持契約で秘密情報の定義を定めることによって、公に知られたくない秘密情報の範囲を個別に設定することができます。不正競争防止法で守られる営業秘密の範囲は限定的であるため、これに該当しない秘密情報を守りたい場合に有効です。
秘密保持契約は契約行為なので、秘密情報を扱う当事者間での合意が必要です。あまりに広範な情報を秘密情報として定めると、受領者側から定義を狭めるよう交渉される可能性があります。
秘密保持契約(NDA)の注意点

次に秘密保持契約の注意点を解説します。実際に秘密保持契約を結ぶ前にチェックしてもらいたいポイントを4つ挙げていますので、参考にしてみてください。
- 秘密保持契約(NDA)締結後に情報開示を行う
- 秘密情報の範囲・目的を限定しすぎない
- 期間を長くしすぎない
- 違反した時の措置を取り決める
それぞれ詳しく解説します。
秘密保持契約(NDA)締結後に情報開示を行う
秘密情報の開示は秘密保持契約を締結してから行うようにしましょう。秘密保持契約の締結前に情報開示してしまうと、秘密情報として扱われない可能性があります。また、業務提携などの本契約時にまとめて秘密保持契約をする予定であったが、条件が合わず本契約に至らなかった場合なども同様のリスクが生じます。
そのため、本契約締結前の打ち合わせにおいて、秘密情報をやり取りする必要がある場合は、事前に秘密保持契約を締結しておくとよいです。
秘密情報の範囲・目的を限定しすぎない
秘密保持契約では、契約条項にどのような情報を秘密情報とするか定義づけと、秘密情報を開示する目的を設定する必要があります。
秘密情報の範囲や目的を正確に記載することは、双方の認識ずれを防ぐために必要です。しかし、範囲を限定して記載すると漏れが生じやすくなり、想定外の情報漏えいを許してしまうことになります。
たとえば、「本件業務のために相手方に書面、電子または口頭により開示される全ての情報のうち、開示当事者が秘密保持すべきと指定したもの」など広く定義づけるようにしましょう。
期間を長くしすぎない
秘密保持契約を締結する際は、当事者間で有効期限を定める必要があります。有効期限は提供する情報の性質に合わせて適切に設定する必要があるため、方法はさまざまです。
たとえば、有効期間を1年と定め、契約当事者から特に申し出がなければ毎年自動更新する方法や、取引終了後も秘密情報の管理義務を存続させるために一部の条項のみ契約終了後も一定期間効力を残すといった方法があります。
一方で、永久に管理義務が存続するなど開示者側が極端に有利な期間設定をすると、受領者側にとって情報の管理コストがかかり続けることから、短くするように求められる場合があります。
違反した時の措置を取り決める
秘密保持契約に違反して受領者側が営業秘密を第三者に開示するなどしたことがわかった際、これ以上営業秘密を扱わないように差止請求や損害賠償請求できる規定を設けるようにしましょう。
不正競争防止法に定める営業秘密に該当する情報が受領者側によって漏えいした場合は、同法に基づいて差止請求(同法第3条)や損害賠償請求(同法第4条)が行えます。同法によって保護されない営業秘密以外の秘密情報が漏えいしたときの対応を、秘密保持契約締結時に取り決めておきましょう。
損害賠償の金額は、あらかじめ損害の予定額を設定する方法や、実際の損害額に応じて請求するなどの方法があります。
秘密保持契約(NDA)の条項
秘密保持契約を締結する際、契約書に盛り込むべき条項を解説します。経済産業省が不正競争防止法に関するページの中で公開している秘密保持契約書のひな形を参考に紹介します。
<秘密保持契約書に記載する条項>
1.秘密情報の定義
2.受領者側の秘密情報の取り扱い(管理方法、目的外利用の禁止など)
3.秘密情報の返還義務
4.損害賠償・差止請求
5.有効期間・存続条項
6.その他(協議事項や管轄裁判所など)
また、これらの秘密保持に関する条項を業務委託契約書などに秘密保持条項として盛り込むことも可能です。
秘密保持契約(NDA)に関するよくある質問
最後に秘密保持契約に関してよくある質問とその回答を紹介します。秘密保持契約について同様の疑問を感じている方は参考にしてみてください。
- 秘密保持契約(NDA)締結は義務付けられている?
-
秘密保持契約の締結は法律で義務付けられたものではありません。しかし、秘密情報を開示して取引を行う際、秘密保持契約を締結することで受領者側に秘密保持を義務付けられるため、情報漏えいのリスク軽減につながります。
- 秘密保持契約(NDA)に収入印紙は必要?
-
秘密保持契約書に収入印紙は不要です。印紙税が必要な契約については印紙税法で定められており、国税庁のホームページに印紙税が必要な文書の一覧(※)が掲載されています。
秘密保持契約(NDA)は印紙税が必要な文書のいずれにも該当しないため、収入印紙は不要です。
ただし、契約書の中に秘密保持条項として盛り込む場合には、その契約の内容について収入印紙が必要であるか確認する必要があります。(※)https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7140.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7141.htm - 秘密保持契約(NDA)は電子契約でも締結可能?
-
秘密保持契約は電子契約でも締結が可能です。電子署名法第3条により、同法で定める電子署名が行われているものは有効な契約となります。
契約書作成の手間や郵送費用などを削減できるため、電子契約による秘密保持契約の締結も有用です。
秘密保持契約(NDA)を締結して安全な取引を行いましょう

今回は秘密保持契約(NDA)の定義や守られる秘密情報、締結のメリットなどを解説しました。秘密保持契約によって不正競争防止法で保護されるよりも広い範囲の秘密情報を守ることができます。
秘密情報保護の重要性が高まる中で、秘密保持契約を有効に使って情報漏えいリスクを抑えた安全な取引を進めましょう。