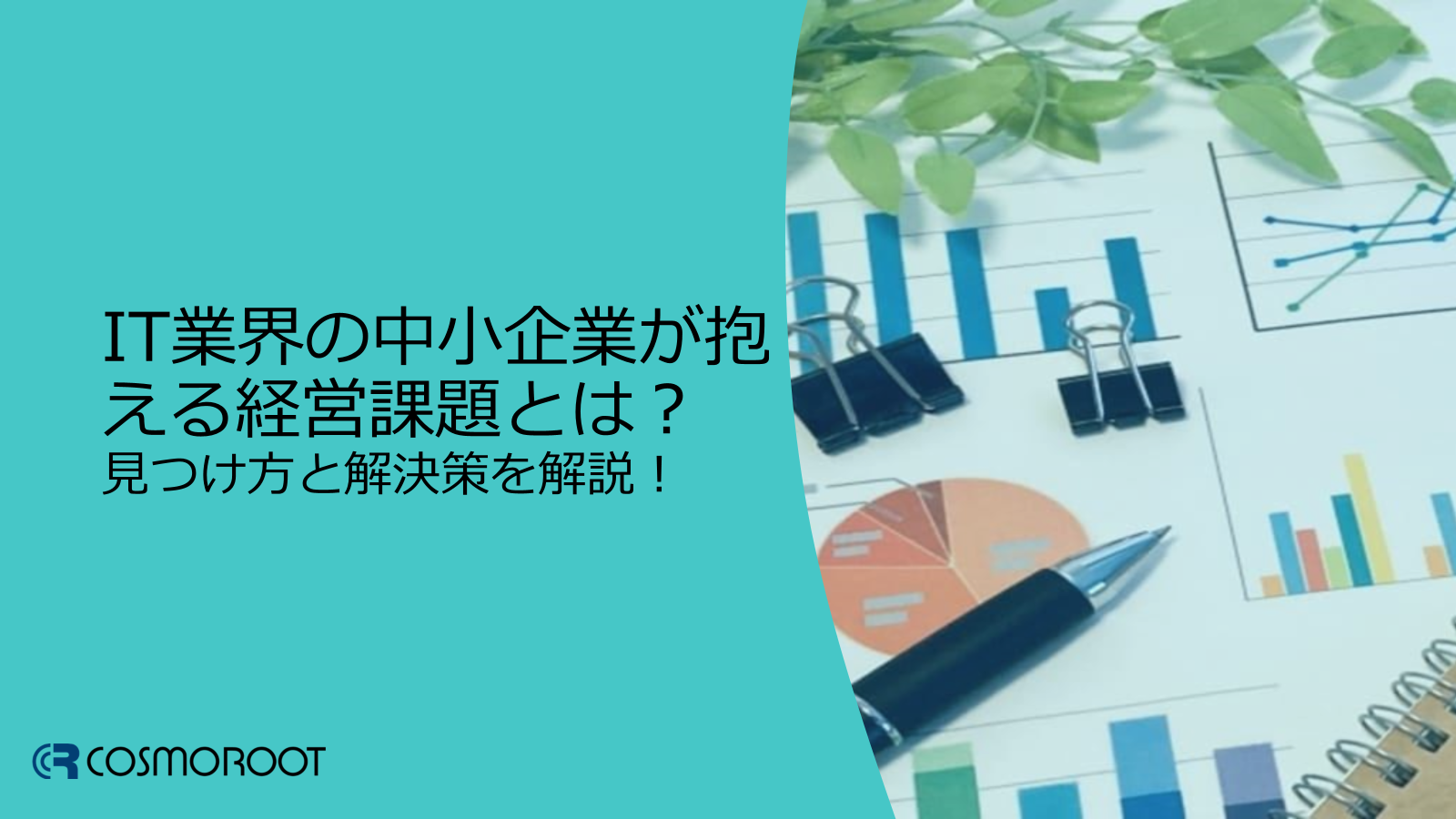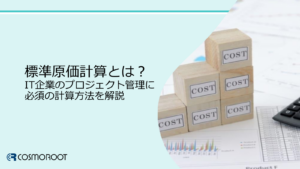経営課題とは、企業が成長を続けるうえで適切に設定し、解決していくものです。経営課題には収益性の向上や人材不足など幅広い内容が挙げられます。
本記事では、中小企業庁や日本能率協会の調査結果を基に、経営課題の定義や具体例、解決策と見つけ方を解説します。
特にIT業界の中小企業が抱える課題にフォーカスして紹介するので、IT企業で経営企画を担当されている方は最後まで読んでみてください。
経営課題とは

経営課題とは、企業が目標とするビジョンや達成したいミッションと現状との間にあるギャップを解消するために、解決すべき課題です。企業が成長を続ける上で適切に設定し、乗り越えていくことが必要です。
経営課題は固定されるものではなく、企業の成長ステージや業界動向、国内・海外の状況に応じて変化します。また、事業規模やビジネスモデル、業界の成熟度によって経営課題は変わってくるため、企業ごとに抱えている課題は異なります。
主な経営課題の例

企業ごとに経営課題は異なりますが、大きく6つに分類されます。
本章では、日本政策金融公庫が公表する「2024年4月全国中小企業動向調査(中小企業編)」と一般社団法人 日本能率協会「日本企業の経営課題2023」の内容を基に、中小企業が抱える主な経営課題の例を紹介します。
収益性の向上
収益性の向上は中小企業にとって大きな課題です。先述の調査でも上位に挙がっており、中小企業庁においても収益力改善支援策が実施されるほどです。また、公益財団法人日本生産性本部が公表する「労働生産性の国際比較」では、日本の時間あたり労働生産性は、OECD加盟国38か国中30位の52.3ドルでした。これは1970年以降最も低い順位で、日本は4年連続で順位を下げています。収益性の向上は日本全体が抱える課題の一つといえるでしょう。
人材不足
人材不足も中小企業を悩ませる大きな課題です。総務省の「2023年人口推計」によると、日本の総人口は13年連続で減少しており、減少幅も12年連続で拡大しています。
日本全体で人口減少が大きな問題となっていますが、IT業界ではさらに深刻な状況です。経済産業省の「IT人材需給に関する調査」ではIT人材は既に不足しており、不足幅は拡大を続け2030年には最大約79万人に上るとされています。また、現在のIT人材の不足感について、独立行政法人情報処理推進機構の「DX白書2023」では、83.5%と多くの企業においてDX人材の不足を実感していることがわかっています。
売上拡大・販売力強化
売上の拡大は企業の成長に直接結びつくため、全国中小企業動向調査で経営課題として挙げている企業が最も多いです。
既存顧客からの売上を伸ばすのか、新規顧客を獲得するべきなのか、営業スタッフの営業力向上に注力すべきなのか、多くの企業が頭を悩ませるポイントです。
業界や商品によっては、広告を用いた商品のブランディングなども選択肢に上ります。
事業基盤の強化
事業基盤を強化して足腰の強い経営体制を構築したいと考える経営層は少なくありません。既存事業の市場価値を向上させ、業界における競争力の強化や、取引額が大きい顧客の多数獲得で事業基盤は固められます。
事業基盤を固められれば、経営体制に安定した柱ができるため、次の挑戦がしやすくなります。
新商品・サービスの開発
市場に求められる新商品の開発は、どの業界においても課題として存在します。
新たな商品・サービスを開発することで市場におけるポジションを大きく変化させる契機になる可能性があるためです。
先に挙げた事業基盤の強化や市場競争力の向上にもつながるため、何か良いアイデアはないかと頭を悩ませている方も多いでしょう。
デジタル技術の活用
生産性の向上・業務効率化を目的としたデジタル技術の活用も多くの企業で課題として挙げられています。何を目的としてどの業務にデジタル技術を活用してよいか見えていない中小企業も少なくないでしょう。「DX白書2023」では、DXに一部でも取り組んでいる企業は69.3%に上ります、しかし、同白書では都心に位置する大企業ほどDXが進んでおり、中小企業や所在地が地方になるほど普及していない実態が浮き彫りになりました。
経営課題の解決方法

次に前章で取り上げた主な経営課題の解決方法をそれぞれ解説します。前章で挙げた内容と近い経営課題を抱えていると感じた場合は、ぜひ参考にしてみてください。
収益性の向上
収益性の向上において、値上げや付加価値の高い商品・サービスの開発などが解決策として挙げられますが、最も即効性が高いのはコスト削減です。
どの作業にどれくらいの工数を要しているのかを細かく把握し、無駄や重複するものを見つける作業から始めましょう。
そのためにも、各スタッフが何の作業にどれくらいの時間を割いていて、どの作業をどれくらいの金額で外注に依頼しているかを洗い出すことが必要です。
人材不足
人材不足においては、今のスタッフの生産性を向上させることと、人材募集の両輪で進めていくことが大切です。
個々の生産性を高めていくためには、各スタッフが得意とする領域と業務内容をマッチングさせ、ポテンシャルを十二分に発揮してもらう必要があります。また、スタッフが目指すキャリアプランを達成できるように人員配置を行い、モチベーションを高く保って仕事に当たってもらうことが重要です。
適切に人材配置を行ったうえで、不足するスキルや人員について新しく募集するのが望ましい体制です。
これらを行うにはタレントマネジメントシステムを導入して、スタッフのスキルや経歴、キャリアプランなどを管理する必要があります。
売上拡大・販売力強化
売上や販売力の強化には、営業スタッフの増員や営業拠点の拡大といった量的な手法が一般的ですが、一方でこれらはコストも増大します。
ナレッジの共有や案件ごとの工数管理によるリソースの最適化といった質的な手法が重要です。
案件ごとに成約・取引金額拡大に至った顧客とのやり取りや経緯を営業スタッフやマネージャーと共有することで、売上拡大につなげることができます。スタッフ・マネージャー間での顧客情報の共有には、ツール導入や定期的なミーティングなどの手法が考えられます。
事業基盤の強化
事業基盤の強化を目的として、既存顧客の売上を伸ばすためには関係性の強化が必要です。今の担当者による属人的な売上では継続的な取引や売上の拡大は望めません。そのため、打ち合わせ内容や担当者の個性など詳細な情報を部署全体で共有し、担当が替わってもシームレスに対応できる体制づくりが求められます。
このような情報共有においては、CRMなどのツール導入が解決への近道になります。
新商品・サービスの開発
新商品の開発にあたって収益性の向上などの課題を解決したい場合は、独自技術などによる付加価値のある高単価商品を開発することを主軸に置くと良いです。顧客はベネフィットのある商品であることを理解すれば、低価格であることだけを理由に商品選定を行わないためです。
顧客ニーズについてアンケートなどの市場調査を通して仮説を立て、技術や商品の開発に取り組みましょう。技術開発においては、行政機関の補助金などを得られれば、開発コストを抑えることも可能です。
デジタル技術の活用
デジタル技術の活用にあたっては、企業文化の刷新と目的の明確化が大切です。
中小企業庁が公表する「2021年版中小企業白書」では、デジタル化推進に向けた課題として、「アナログな文化・価値観が定着している」が最も多い回答でした。IT業界においては「明確な目的・目標が定まっていない」と回答した企業が多かったです。
デジタル技術を導入することが目的になっていたり、既存業務をデジタルに置き換えることだけがデジタル化と考えていては前に進みません。
現場から意見を吸い上げた上で経営層とすり合わせを行い、進めていくことが大切です。
経営課題の見つけ方

最後にそもそも自社の経営課題が明確に見えていない場合、どのようにして経営課題を見つければよいか、見つけ方を3つの観点から紹介します。
経営戦略や経営企画に携わっている方は、自社が抱える課題をどのようにして見つけるか参考にしてみてください。
収支管理の徹底
経営課題の発見には数字の管理が欠かせません。単なる資金の出入りだけを管理していても部署や部門ごとの収支しか見えていない「どんぶり勘定」の状態になっているため、経営課題を見つけるのは難しいです。
経営課題を把握するためには、案件ごとにどれだけの人件費や外注費が発生し、それに対してどれだけの収入があったかを管理する必要があります。これによって、収益性の高い案件や事業に経営資源を集中させるための取り組みや課題が見えてきます。
業務フローの可視化
各案件がどのような業務フローを経て進行しているのか、そのためにどれくらいの工数が発生しているのかを精緻に把握することも重要です。収支上は利益の多い案件であっても、スタッフの人件費を差し引くと実はマイナスだったというのはよくある話です。また、多くの工数が発生している案件であっても、効率化や他のスタッフと重複している作業を見つけて省力化に成功すれば、収益性を向上させられます。
社員の保有スキル・目標の把握
スタッフがそれぞれどのようなスキルを保有し、将来どのようなキャリアを歩んでいきたいと考えているのか、目標とその進捗を把握することが大切です。これによって、生産性を高めるための人財配置が行えます。
また、キャリアプランを踏まえた配置を行うことで、スタッフのモチベーションが高まり個々の生産性を向上させる効果もあります。適切な配置が行えると、前の部署では活躍できていなかったスタッフが力を発揮するようになるなど、人財という経営資源の最適化が可能です。
各部門の組織状況の確認
各部門の組織状況を改めて確認することも、経営課題の発見につながります。
各部門・部署が担当する業務領域を確認し、重複するところはないか想定される業務量に対して人員過多になっている部署はないかと総点検してみましょう。これによって、人材配置の最適化を目指すための課題や施策が考えられます。
また、部署ごとの担当業務や達成目標を適切に設定することで、人事評価制度の見直しにもつながります。
経営課題設定のために自社の現状を把握しよう!

経営課題は自社の現状と目指すビジョンとのギャップを埋めるために解決するべき課題であるため、まずは自社の現状を正確に把握することが経営課題解決のための第一歩です。
現状把握にはExcelなどの表計算ツールでも管理は可能ですが、情報分析や全社的な情報の可視化には専用ツールの導入が近道です。
NeWARPでは、人財や収支、作業工数などの経営資源をリアルタイムに可視化するため、どの部門がどのプロジェクトで収益を上げているかが一目でわかります。従業員のタレントマネジメントも行えるため、今回紹介した経営課題を見つけ、解決策を導き出すのに効果的です。
NeWARPはクラウド上で提供しているため、契約後すぐに使用可能な点です。以下のリンクから詳しい情報をご覧ください。
NeWARPはこちら